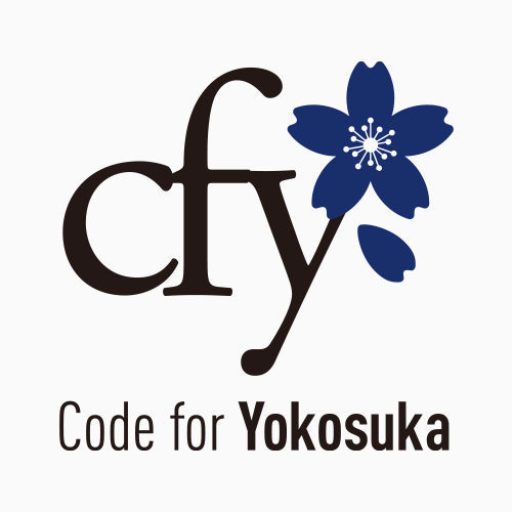【2020.3.12】Civic Hack Night@オンライン
※過去記事をあげています。Code for Yokosukaの活動のご参考に!

Code for Kanazawaと合同開催!
日本にも新型コロナウイルス感染者が出始め、テレワーク・在宅勤務の推奨や学校の急行などが相次ぐ中、
「オンライン会議ってどんなツールを使ったらいいかわからない。。」
「情報共有するのに遠隔で使えるツールって何があるの?」
そんな声がニュースを始め、周囲でも多く聞かれるようになってきました。
情報通信業で働く私たちにはある種「当たり前」になっている事も、異業種含め使用したことのない企業・団体・学校の頭の中は《???》の混乱状態。
Code for Yokosukaとして「ITを用いて地域課題を解決する」というビジョンを掲げている中、これはちゃんと向き合わなくてはいけない問題だと痛感しました。
団体内で「ウェビナーをやろう!」という決意が固まったものの、さて私たちもオンラインセミナー開催なんて初めて。
どんな話題がBESTなのか?、配信ツールは?、セミナーの時間ってどのぐらいがちょうどいい?
そんな色々な壁にぶち当たっていると、FacebookでCode for Kanazawa(石川県金沢市が拠点のシビックテック団体)さんが月一開催で行なっている「Civic Hack Night」をオンライン開催でやるとの情報が…!!
ここから、一緒にやりませんか!?の流れになりました。
しかし開催まで2日しかない、準備期間はほぼなくぶっつけ本番の流れの中で告知もほとんどできず。。。
それでも共に開催してくださったCode for Kanazawaさんには感謝しかありません。
Civic Hack Nightの内容
オープニングセッション&シビックテックとは?
そもそも主催のCode for Kanazawa、そしてCode for Yokosukaってどんな活動をしているの?の疑問にお答えする形で各団体の説明をさせて頂きました。
HPを見てくださっている方は何となくご理解いただいているかと思いますがCode for 地域の名前が付いている団体は主に《シビックテック》と呼ばれる、「ITで地域課題を解決していこう」という取り組みをしている団体です。
ただ、地域課題だけに特化するわけではなく、「こんなもの作ってみたい!」など個人発信から構想するアプリケーションやWEBサービスを作っているところもあります。
一般社団法人の法人格を取っている団体も多くありますが、Code for Yokosukaのように任意団体として地域活動をしているところもありますし、形態は様々です。
ちなみに2013年に初めてこの《シビックテック》の活動を始めたのはCode for Kanazawaさんです!
企業で使っているITツール!オンラインツール!
冒頭でもお伝えした通り、「テレワークで使えるツールってどんなもの?」や「情報共有で便利なツールってどんなもの?」を中心に、今回のパネラーである皆さんの各企業が実際に使っているツールのご紹介をさせて頂きました!
・ zoom
今回のオンラインセミナーでも使用したこの「zoom」というオンライン通話ツールです。
実は2種類あって、特定の参加者を招集しての会議や打ち合わせに使用される《zoom ミーティング》と、オンラインセミナーやオンラインイベントのように大人数だったり参加者が不特定多数になる場合に使用される《zoom ウェビナー》というものがあります。
《zoom ミーティング》は全員の顔が表示されたり(設定によりビデオをオフにできます)zoomの設定側で定期ミーティングとして設定が可能となり毎回URLの発行をしなくても良く手間が省けるよね。といったメリットがあります。
また、1つのミーティング内で部屋を分ける事も可能で、全体会議からAチーム会議・Bチーム会議・Cチーム会議と別れ、最後にまた全体会議!などの設定もできるそうです。
ミーティングと言えども、こちらの場合は100名まで同時参加が可能です。
100人のミーティングって結構すごいですよね(笑)
デメリットとしては「zoom」のアカウント設定が必要といったところでしょうか。そんなにややこしい設定はないのでご安心を。
《zoom ウェビナー》はパネラー(1人から複数名まで開催可能)側とセミナー参加者側が完全に別れているイメージで、セミナー参加者側の顔や音、声はパネラーや他の参加者には聞こえない設定になっています。
ミーティングと違い、セミナー参加者は完全に聞く側に徹することができます。
また、《zoom ミーティング》で必要なアカウント設定も不要なことから、参加のハードルが低いとも言えますね。
「とにかくこのURLを押して参加して!!顔も声も共有されないから!」でと伝えるだけで、イベントの参加を促せる訳です(笑)
今回のイベントではzoom以外ご紹介ができなかったのですが、オンラインで会議をしたい!という要望があれば、こちらをまず使ってみていただけるといいかもしれません。
Slack
メール以外で、気軽に連絡のやり取りができるツールってあるの?
そんな声おすすめなのが「Slack」です。
ある一定の上限までは無料で使用できるので、まずお試しに登録してみてもいいかもしれません。
情報共有をしたい方全員にSlackの登録が必要になってきますが、Slackの中でも部屋を作ることができ(チャンネルと呼ばれます)、メールのTo・CCを使わなくてもこの部屋に文章を投稿するだけで部屋のみんなが閲覧できるというものです。
チャンネルは複数設定できるので、例えば「教育指導教員」とか「小4教員」などの部屋を分けておけば、メールのようにごちゃごちゃしてしまう事もありません!
ちなみにチャンネルは英語(ローマ字)で作成しなくてはいけないというルールがり、個人的に少し「むーーー」としたりもしています(笑)
また、個人宛にもメッセージを送ることができるので(ダイレクトメッセージ=DMと呼ばれます)、個別に相談したい・共有したいこともこのSlackの中で行うことができますよ!
もちろんファイルの共有やURLの共有なども簡単にできるので、どこで共有したっけ。。。となる事も少なくなります!
Googleドキュメント・Googleスプレッドシート
情報共有で個人的にもっとも使いやすく、喜ばれるのがこの「Googleドキュメントとスプレッドシート」。
簡単に説明すると、Word(これがドキュメントに当たります)とExcel(こちらがスプレッドシート)をリアルタイムで共同作成できるツールなのです!
よく、「あれ?どれが最新のファイルだ?」となってしまうところも、これらのツールは更新してもファイルは1つしかないので、最新ファイルを探す・間違える心配もありません。
「でも、提出はWordやExcelじゃなきゃダメなんだよ。。」
という悩みにもきっちりコミット!!
エクスポートという機能を使えば、共同で作成したドキュメントやスプレッドシートもWord・Excelのファイルとして出力できるのです。
この他にも、簡単にフォーム(申込みフォームや問い合わせフォーム)を簡単に作れる機能や、スライド(これはPowerPointに当たります)を共同作成できたりもします。
使用するにはGoogleアカウントの作成が必要となりますが、使用する保存データの上限を超えない限りは無料で使用することができます!
共有用に1つのアカウントを作成し、複数人で管理もできますので(推奨されてるかは謎です。ごめんなさい!)わざわざ人数分のアカウントを作成しなくても大丈夫です。
最後にまとめると…
準備期間が少ない中、100%充実した内容をお伝えすることはできませんでしたが、開催してよかった!!というのが本音です。
とにかくやってみよう。人のためになるかもしれないし。
団体の自己満足かもしれませんが、Code for Yokosukaとして新しい第一歩が踏み出せたような気がしました!
こちらのウェビナー、録画しているのですが、まだ編集できていません!!!(2020.4.14現在)
広く長く見ていただけるように、きちんと公開させていただきますので、しばらくお待ちください。
イベント風景